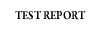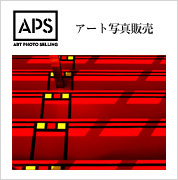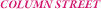
- Artdirector
日高英輝
- 2017.03.22
ある商品のカタログ撮影で、会心のフォトディレクションと自負できる写真が仕上がり、
盤石の自信を持って社長プレゼンに臨んだ。
社長はテーブルに並べたプリントを、じっと食い入るように見ていた。
長い沈黙の後、「何かが違う」とポツリと言った。
当然食い下がったが、「なんか違う」という答えなき答えに理屈など通じるわけもなく。
冷静を装いながら、あらゆるシミュレーションを頭の中で行っていると、
社長が突然「どっちがいいと思います?」と2枚のプリントを取り上げた。
ひとつは会心のフォトディレクションの1枚、もうひとつは、フォトグラファーに
自由に撮影してもらったものだった。当然、社長はそんなことは知らない。
真意は計りかねたが、アートディレクターという立ち位置でなく、
客観的にその2枚と対峙し、「個人的に好きなのはこっちです」と自由撮影のほうを指差した。
「ですよねぇ。私もこっちに惹かれます」。
その写真は商品の超クローズアップで、何が写ってるのか判別できないような写真だった。
カタログ中で遊びページ用として撮影してもらった、言わばイメージカット。
「こんなイメージで全商品を撮影したものを見てみたい」と社長は言った。
フォトディレクションの敗北。
綿密なコンセプトワークと周到な準備、ベストなスタッフィングで挑んだディレクションだったが、
フォトグラファーに自由に撮影してもらった一枚の写真に、すべてを持って行かれてしまった。
再撮影は立ち会わないことにした。ノンディレクションというディレクション。
やけくそではなく、それがいいと思ったからだ。
困惑するフォトグラファーに伝えたのは、
「密室で恋人のヌードを撮るように商品を撮影してほしい」ということだけだった。
なおさら混迷は深まったことだと思う。
後日、撮影し終わったので見に来てほしいとスタジオに呼ばれた。
モニターに映し出された写真をみた。じっと見た。
艶やかで、ミステリアスで、エロティック。
理屈を超えた強さがその写真にはあった。
賞賛の言葉を投げかけると、やつれた表情のフォトグラファーは少し笑った。
目的とかコンセプトに寄り添った写真を、簡単に飛び越える写真というものがある。
「良いものが良いにきまっている」のだ。
コマーシャルフォトは"目的"をもった表現手段だ。
しかし、それを追求すればするほど、写真本来の魅力が失速していく場合もある。
そこにこの仕事の難しさとやり甲斐がある。
監督と放任、狙いと偶然、会議室と現場、アートディレクターがどちらに軸足を置くかで、
同じ被写体でも仕上がり違ってくる。文字どおり写ってしまう。
写真とはまったくセンシティブな表現だと思う。
僕にとってのフォトグラファーとは、イメージに翼をつけてくれる人のことを言う。
貧相な発想やアイデア、数多ある事情などを軽々と突破し、見るに耐えうる表現まで高め、
感銘をあたえる領域まで連れて行ってくれる。
これまで、どれほどプロフェッショナルな写真家たちに救われてきたことか。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
『SHOOTING』創刊から足かけ6年にわたって書かせていただいた本コラム。
今回をもちまして最終回となりました。
6年間で20本ということは、年間3〜4本ほどの更新頻度となり、
スピード感命のwebマガジンとしては、まったくもって欠陥コンテンツだったと思いますが、
辛抱強くお尻を叩き続けてくれた坂田編集長には、ごめんなさいとともに感謝の意を表します。
これからも、写真と映像のプロ向けマガジン『SHOOTING』をよろしくお願いします。
日高英輝

日高英輝 - Artdirector
宮崎県生まれ。グリッツデザイン主宰、アートディレクター。
グラフィックデザインをベースに多領域で活動中。
主な受賞歴、JAGDA新人賞、NYADC銀賞、日経広告賞グランプリなど多数。
WEB: http://gritz.co.jp/

- 2017.03.22フォトディレクションの周辺 vol.20 「for All Photographers.」〜最終回〜
- 2016.10.07フォトディレクションの周辺 vol.19 「Life goes on.」〜The Best of LIFE〜
- 2016.02.27フォトディレクションの周辺 vol.18 「僕らの夢」〜日興コーディアル証券〜
- 2015.09.11フォトディレクションの周辺 vol.17 「ひなたのチカラ」〜宮崎県プロモーション〜
- 2015.02.06フォトディレクションの周辺 vol.16 「EPISODE SW」〜GOOD YEAR〜
- 2014.10.31フォトディレクションの周辺 vol.15 「誰もがいつか失う重さ」~21グラム~
- 2014.08.21フォトディレクションの周辺 vol.14 「夢の中へ」〜井上陽水・氷の世界ツアー2014 LIVE the BEST〜
- 2014.02.27フォトディレクションの周辺 vol.13 「まだ、世界にない、歓びへ」〜LEXUS LS600hL〜
- 2014.01.21フォトディレクションの周辺 vol.12 「丸くはなれない」〜BESSの家〜
- 2013.07.02フォトディレクションの周辺 vol.11 日本の足の皆さんへ」〜NIKE サッカーキャンペーン〜
- 2013.02.06フォトディレクションの周辺 vol.10 「幸福な仕事」〜東海道新幹線30周年キャンペーン〜
- 2012.09.10フォトディレクションの周辺 vol.9 「元気を産もう、宮崎県」〜口蹄疫、発生から終息まで。その2〜
- 2012.06.28フォトディレクションの周辺 vol.8 「元気を産もう、宮崎県」〜口蹄疫、発生から終息まで。その1〜
- 2012.05.23フォトディレクションの周辺 vol.7 「自分の地図を描くこと」〜ミハラヤスヒロ〜
- 2012.01.27フォトディレクションの周辺 vol.6 「安全をつくる仕事」〜TAKATA〜
- 2011.10.31フォトディレクションの周辺 vol.5 「Green Boy」〜GReeeeN〜
- 2011.09.08フォトディレクションの周辺 vol.4 「本は背表紙」〜ホンダブックス〜
- 2011.08.19フォトディレクションの周辺 vol.3 「デザインの山脈」〜カッシーナ・イクスシー〜
- 2011.07.24フォトディレクションの周辺 vol.2 「儚い、だから美しい」〜バカラ〜
- 2011.06.30フォトディレクションの周辺 vol.1 「カバンを撮ってくれるな」 ~ゼロハリバートン~