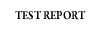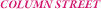
- Producer
うやまりょうこ
- 2015.11.10
イギリス人の日曜日の過ごし方の代表的なものの一つがパブで新聞を読むことです。日本でもサンデータイムズ、インディペンデント、テレグラフなどの新聞の名前を聞いたことがあるかと思います。
イギリスの新聞は週末になると小さい冊子のような別巻がたくさん入ったものが販売になります。普段新聞を読まない人でも、この日曜版だけを読む人も多いです。そこにはコラム、写真の特集、セレブ、スポーツ選手のインタビュー、時事関連の特集、変わったストーリーなどを集めた内容が満載です。
こういった新聞の影響なのか、イギリスのドキュメンタリー写真は大変面白いものが多く見られます。
ドキュメンタリーというと、一般的には戦争や過激なものを撮影するというイメージが強いですよね。しかしイギリスの場合、ストリートフォトフォトに近い、身近なトピックをユーモアや感情を込めて撮るという、日常に根付いたものもドキュメンタリーというカテゴリーに含まれます。
今回は現在も活躍するイギリス独特のドキュメンタリーの写真家を紹介したいと思います。
ありのままのイギリスを撮った第一人者「Martin Parr」(1952-)

©Martin Parr
Martin Parrの作品はいわゆるワーキングクラス(労働者階級)をイギリスの文化として皮肉に、悪趣味でセンスのない、かっこわるいところをありのままにユーモアとして撮影するスタイルで有名です。
上半身裸のおじさんがビールを目一杯に持っている、ぎゅうぎゅうのビーチで泳ぐわけでもなく新聞を読む、ゴミだらけのバス停でフィッシュアンドチップスを食べる。靴下をはいたままサンダルを履く。
これが人々の暮らしである、これがイギリス人であるということを真っ向から撮影しています。
彼は撮影するときファインダーで被写体を見ず、カンでピントを合わせて内緒で撮ることもあるそうです。撮られている人たちが意識していない姿と何となく不安定なフレーミングはここから来ているのかと思います。
彼はこういった人々の暮らしを撮ったドキュメンタリー写真を、一つのジャンルとして確立させ、たくさんの本を出しています。
リバプールで写真を撮り続ける「Tom Wood」 (1951-)

©Tom Wood
リバプールはアイルランドから来た人たちが多く住むエリアで彼もアイルランドからの移民です。60年代のサッチャー政策以降、経済が悪くなったイギリス北部での暮らしは厳しいものでした。またアイルランドからの移民は当時まだ差別を受けることも多くありました。
彼はバスの中の人、バス停で待つ人、バスから見える景色や人たちを集めた写真をたくさん撮っています。郊外でバスに乗るということは車がない、買えないということでもあるので、被写体はどちらかというと貧しい人、社会的にも弱い立場の人であることがわかります。
お天気の悪いリバプール郊外のくたびれた景色の中で負けない人たちの力強い存在、哀愁漂う生活に寄り添うように撮影しています。
特に私がお勧めしたいのは「bus odyssey」という写真集です。毎日毎日バスに乗って撮り続けた力作です。撮られている人は日常を普通に暮らしているのに、どこか違う世界に住んでいる人が間違ってそこにいるような孤高の雰囲気を醸し出しています。
ブックフェアで偶然Tom Woodご本人にお会いすることができました。ご本人もいま写真集のバスから降りたような、普通の人という佇まいでした。『あなたの写真のファンです』と伝えると、逆に『あなたはどういう写真を撮っているの?』と聞いてくれました(私は舞い上がって何を言ったか覚えていません!)。
人間が好きで、初対面の人にさえも警戒させない人間性が写真にもにじみ出ているように思います。(ご本人はウェブサイトがないので新聞社テレグラフから)
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/9895436/Tom-Wood-Photographs-1973-2013.html
固定観念にとらわれない写真「Muir Vidler」(1973-)

©Muir Vidler
スコットランド出身のロンドンで活躍するMuir Vidlerは、サンデータイムズに多くの写真を出しています。彼は文化、政治的にタブーな事柄をユーモアたっぷりに撮影しています。
私は彼のアシスタントをしていたのでたくさんの面白い撮影に立ち会うことができました。中でも印象に残っているのはPeta(アメリカの過激な動物愛護協会、動物実験、毛皮、食肉の反対を掲げています)の創設者、イングリッド・ニューカークの撮影のときのことです。
このときはイングリッド自身を家畜に見立てて、精肉市場で撮影するという目論見です。食肉用の動物がどういう目に遭っているのかを人間に置き換えるという活動の一環です。
早朝6時、カフェで待ち合わせ。カメラマンMuir Vidler はひとりで撮影の許可を取るために市場に入っていきました。30分くらいすると戻ってきて撮影場所に向かいます。
この60才のイングリッドは精肉市場の一角でいきなり真っ裸になりました。そして豚が丸ごと吊り下がっているフックに自分もぶら下がります。撮影時間5分でした。
私がびっくりしたのはどうやってここで撮影させてもらえたのかということです。『どうやって頼んだの?』『何人もダメって言われたけど"なぜか"いいって言ってくれる人がいたんだよね。』この"なぜか"の力。
ユダヤ人のコミュニティーのパーティーに(閉ざされたコミュニティーであることで有名)なぜか入れてもらった、リビアのカダフィーの家になぜか連れて行ってもらえたり。なかなか行くことができない、怖くて行けないところに"なぜか"行って写真を撮ってくることができる不思議なカメラマンです。
Muirの新しい写真集、Everything is Trueが出版予定です。
http://muirvidler.com
毎日の生活の中で、身近なところで撮れる写真であるからこそより難しいこういったドユメンタリー写真ですが、いま注目を浴びてアート写真として認められてきていることでどんどん面白いものがこれからも見られることを期待させます。
紹介した3人のカメラマンも現役、次の作品が楽しみです!

うやまりょうこ - Producer
神奈川県平塚市出身。10BAN スタジオ勤務を経て2004年より、ロンドンに移住しフリーランスでカメラマンアシスタントになる。Nadav Kander, Tim Flach などのアシスタントを経験後、カメラマンとしても活動。オブザーバー新聞、タイムアウトマガジン、ELLE、マリー•クレアなどに写真を提供。イイノメディアプロロンドン支部を経てフリーランスで撮影のプロダクションの仕事に携わる。 イギリスの伝統的ダンス、モリスダンス歴7年。映画好き。日本の小説を読み、イギリス地ビールを飲むのが一番の幸せ。
Twitter : https://twitter.com/RyokoUyama

- 2018.06.07ロンドン秘密基地 第2章 vol.12 Life after the photography
- 2017.09.28ロンドン秘密基地 第2章 vol.11 ロンドン老舗の現像所 Rapid
- 2017.03.28ロンドン秘密基地 第2章 vol.10 Niall McDiarmid インタビュー
- 2016.12.08ロンドン秘密基地 第2章 vol.9 イギリスのクリスマスの風物詩
- 2016.10.24ロンドン秘密基地 第2章 vol.8 番外編でニューヨークの写真家のお話
- 2016.06.15ロンドン秘密基地 第2章 vol.7 レスター優勝で見えてくるイギリスの現状
- 2016.04.12ロンドン秘密基地 第2章 vol.6 2016年春、ロンドンの写真展
- 2016.03.09ロンドン秘密基地 第2章 vol.5 公募を通して世界に挑戦!(3/3) 最終回
- 2016.01.18ロンドン秘密基地 第2章 vol.4 公募を通して世界に挑戦(2/3)
- 2015.12.14ロンドン秘密基地 第2章 vol.3 公募を通して世界に挑戦!(1/3)
- 2015.11.10ロンドン秘密基地 第2章 vol.2 イギリスのドキュメンタリー写真
- 2015.08.06ロンドン秘密基地 第2章 vol.1 東ロンドン限定出版社 ー Hoxton Mini Press